大抵の場合、「バッハのバディネリ」と言うと、正確には「管弦楽組曲第2番第7曲」のことを指します。クラシックの中ではかなり知名度が高い楽曲と言ってもいいこの曲は、1724年~1731年の間にかの有名なヨハン・セバスティアン・バッハによって作曲されました。
曲の紹介
バディネリはフランス語で「冗談」という意味です。因みにイタリア語で「冗談」はスケルツォの事を指します。管弦楽組曲自体がフランス風に寄せて作られているため、曲名にもフランス風の名前が付けられているという訳です。
バディネリは第7曲目、管弦楽組曲の終曲に相当します。なんか軽いアンコールがてら作っちゃった♪みたいなノリなのでしょう、バッハさんにとっては(しらんけど)。
この曲は特にフルートがよく目立ちます。フルート奏者の方々にとってはかなりの頻度で演奏する曲らしいです。
曲に関するエピソードなどはこのくらい。正直、情報量が物足りない気もしますが・・・。
曲の感想
クラシック音楽の構成やら何やらの小難しい理論はきちんと勉強していないため、曲のふんわりした感想みたいな代物を適当に書き綴る事にします。ご了承ください。
この曲を聞いてまずイメージされるのは、黄金の光に照らされた白くてなんか沢山いる天使たち(絵画によくいる赤ちゃん天使)の姿です。まあヴァイオリン・フルート多めピッチ高めのハイテンポ、ぴょんぴょん跳ねてる系の曲というのは大抵メレンゲ入りケーキみたいな白、黄色、ふわふわ!というイメージが多いので、妥当と言えば妥当な範囲の感想なのではないでしょうか。
ただ、特筆すべきなのはこれがバッハの曲であるということです。バッハ特有の大御所の雰囲気をまとった重厚感に加え、バロック時代の曲なので、いくらメレンゲ入りだろうといかんせん荘厳かつ生真面目さが抜けきらない仕上がりとなっております。ケーキの土台がスポンジ生地ではなくてずっしり重いタルト生地だった!みたいなイメージです。トッピングはイチゴの代わりにマジパンかホワイトチョコでできたちいちゃな天使が乗っかっています。ここがポイントで、赤ちゃん天使の顔は決してニコニコさせてはいけません。バッハの様ないかつい顔をさせておきましょう。羽根部分は黄、もしくは金に着色しても可。
これでドイツ・バロック・バッハのトリプル超重量を融合させたフランス風バディネリケーキの完成です。皆さんもバディネリを聞きつつメレンゲを「あー白身と黄身分けるのめんどくせー」とか思いながらふわっふわに混ぜて、美味しいケーキを作ってみましょう。
以上、バディネリケーキの作り方でした。
バディネリを摂取するとどうなるか
バディネリは別称、「聞く麻薬」と呼ばれています。一日一バディネリを摂取すれば、貴方は溢れ出す幸福感と全能感とドーパミンとオキシトシンに導かれ、神々がおわす天上に昇る決心をするでしょう。そして、いかつい顔をした天使が貴方をお迎えするため、貴方がいる場所に向かって大移動を始めます。
ただしこの曲、1分30秒弱とバチクソに短いので、天使が下界に降りきる前に曲が終わってしまいます。するとどうなるか。天使たちはたちまち元いた天界に帰ってしまい、後にはバディネリを摂取したにも関わらず逝けなかった悲しき人間の残骸が取り残されます。
【悪魔】「どう、また聞きたいでしょう?」
こうして貴方はまたバディネリを聞きます。以下、無限ループです。
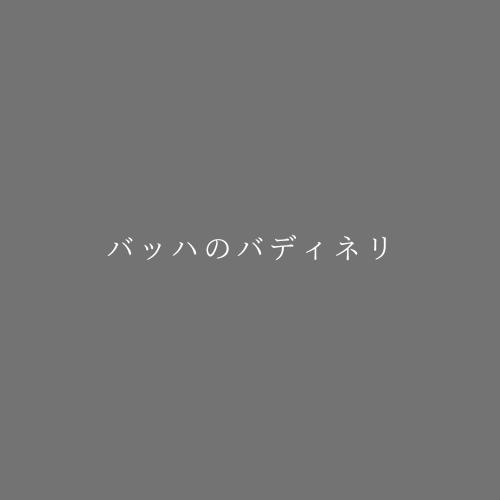

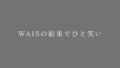
コメント